「金融システム改革」TOPICS!2025年10月版

GESARA社会の基盤となる「金融システム改革」に関連したTOPICSをご紹介。【10月版】です。
目次
イランのアヤンデ銀行破綻!イラン金融システム改革


イラン政府は先日(現地時間10月25日)、国内最大級の民間銀行の一つであるアヤンデ銀行(Ayandeh Bank)の破綻を正式に宣言。同行の資産と負債は国営のメリ銀行(Bank Melli Iran)が吸収し、事実上の救済措置として再編が進められています。
この破綻は、同国の現代銀行史上でも最も深刻な事例の一つとされ、国内外に大きな衝撃を与えている模様です。
破綻の背景:制裁と経済停滞の連鎖
アヤンデ銀行は2013年に設立され、全国で約270支店を展開するなど急速に成長しました。しかし、近年は米国・EUによる金融制裁が長期化し、外貨決済や海外取引が制限された結果、資金繰りが悪化。
不動産関連投資の失敗や、政治的な縁故融資による不良債権の膨張も重なり、経営危機に繋がったと考えられています。
イラン政府対応と金融安定への懸念
イラン中央銀行は破綻発表と同時に、預金者保護と金融システムの安定を最優先に措置を取ると発表。
しかし専門家らは、「アヤンデ銀行の問題は氷山の一角に過ぎない」と指摘しており、制裁下での外貨不足、監督体制の緩さ、国営企業への過剰融資などが相まって、他の民間銀行にも連鎖的な破綻リスクが高まっていると警鐘を鳴らしている状況です。
市場・国際社会の反応
破綻発表後、テヘラン株式市場では金融株が急落し、通貨リアルの対ドル相場も下落。
国際的には、IMF関係者が「イランの金融セクターは極めて脆弱な構造を抱えており、制裁解除なしには回復が困難」との見解が示さされています。
一方で、中国やロシアなどイランと経済連携を進める国々は、新たな金融支援や決済協力の可能性を模索しているといった動きもあります。
今後の展望
今回の破綻は、イラン政府が進めてきたデジタルリヤル(CBDC)導入計画にも影響を与える可能性があります。中央銀行のデジタル通貨構想は、国際決済の制裁回避を狙う戦略の一環とされていますが、民間金融機関の信頼低下がその実現を遅らせる可能性が出てきたことに。
Qプランの視点からは、原則的に「単純な中央銀行デジタル通貨」を阻止する事が求められており、そういう意味では、今回の出来事が
Qプランに沿った「金融機関の再編(改革)」と「イラン国内での中央銀行デジタル通貨の排除」に繋がる
可能性がありそうです。
日本初・円建てステーブルコイン発行へ─JPYC社が「JPYC EX」10月27日始動!


2025年10月24日、東京を拠点とするフィンテック企業 JPYC社は
円建てステーブルコイン「JPYC」の発行・償還を担う専用プラットフォーム「JPYC EX」を 10月27日午後1時 に公開する
と発表しました。
これにより、国内で初めて、資金決済法上「電子決済手段」として扱われる円建てステーブルコインの発行がスタートすることになります。
背景(法整備など)と制度的意義
日本では、2023年に改正された資金決済法により「通貨建てデジタル資産(ステーブルコイン等)」の法的位置づけが整備されました。
中でも、JPYC社による「JPYC」の発行は、国内初の「円ペッグ型」ステーブルコインとして注目されており、発行にあたっては
銀行預金および日本国債(JGB)を準備資産として1:1で円と連動させるモデル
が示されています。
また、機関投資家・ヘッジファンド・ファミリーオフィスなどを初期ユーザーとして想定しており、法人間の資金決済、クロスボーダー送金、ブロックチェーンを活用したワークフロー統合といった実用的なユースケースを目的としているようです。
「JPYC EX」が果たす役割と運用スキーム


この「JPYC EX」プラットフォームは、ユーザー(個人・企業)からの円預託を受け、その円預託額に応じて同額のJPYCトークンを発行・償還を行うためのシステムとなっています。
具体的には次のような流れとなる見込みです。
利用者が銀行口座等から円を送金 → JPYC EXに預託
JPYC EXが対応するチェーン上で「1 JPYC=1 円」のトークンを発行
利用者はそのトークンを用いて決済・送金・業務連携など
利用者がトークンを返却 → JPYC EXが円を返付し、トークンは償却
JPYC社の発言によれば、発行規模が拡大すれば、その分だけJGBなど安全性の高い準備資産を積み上げ、発行体の安定性・信頼性を確保する方針とのことです。
今後の展望・利用シーン
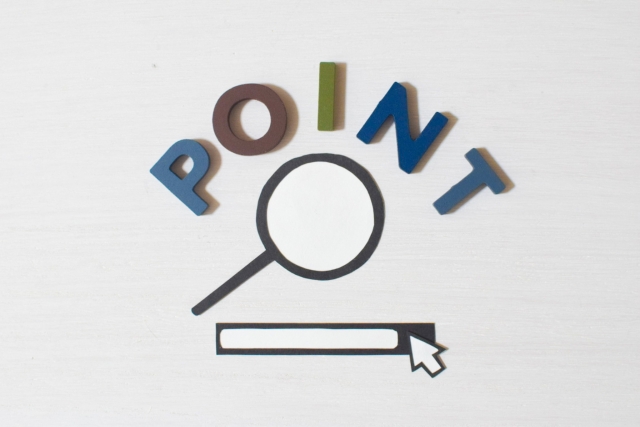
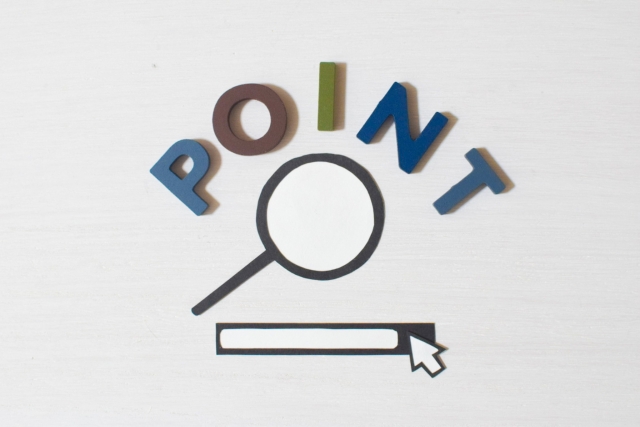
JPYC社が提示しているロードマップおよび市場観察から以下のような展望が考えられます。
1)法人・機関利用の拡大
初期段階では、資金量の大きな法人・機関が主なターゲットに。送金・決済・ブロックチェーン連携など、従来の銀行ネットワーク/決済システムを補完・代替しうる仕組みが想定されています。
2)クロスボーダー送金・国際展開
将来的には「デジタル円」の姿として海外でも流通しうる可能性が示唆されており、円のグローバル・ユーティリティ強化という観点でも注目されます。
3)日本国債市場への影響
発行体が円建て国債を準備資産として積み増す構造のため、国債需要の底上げにつながる可能性があります。市場では「ステーブルコイン発行体=新たな国債買い手」という視点も出ています。
4)決済インフラ・業務プロセスとの連携
プラットフォーム公開を契機に、ERP・会計システム・企業の資金管理インフラとの連携が進むと見られ、現金・預金主導の従来型資金決済からデジタル資産活用への移行を促す役割も期待されます。
日本におけるGCR(世界通貨改革)・RV(通貨価値再評価)の進展に!?


今回の出来事(円建てステーブルコインJPYCの発行)は、日本におけるGCR/RVを促進させる具体的な施策となります。
想定通りのタイミング(新首相の誕生)にて、想定していた「円建てステーブルコイン」が具現化してくるということ。以前からお話しているように「日本」は、Qプランに沿った金融改革の先端を歩んでおり、ここまで順調に推移していることがわかります。
XRPの新金融システムが大きく前進!?リップル社がGTreasuryを10億ドルで買収
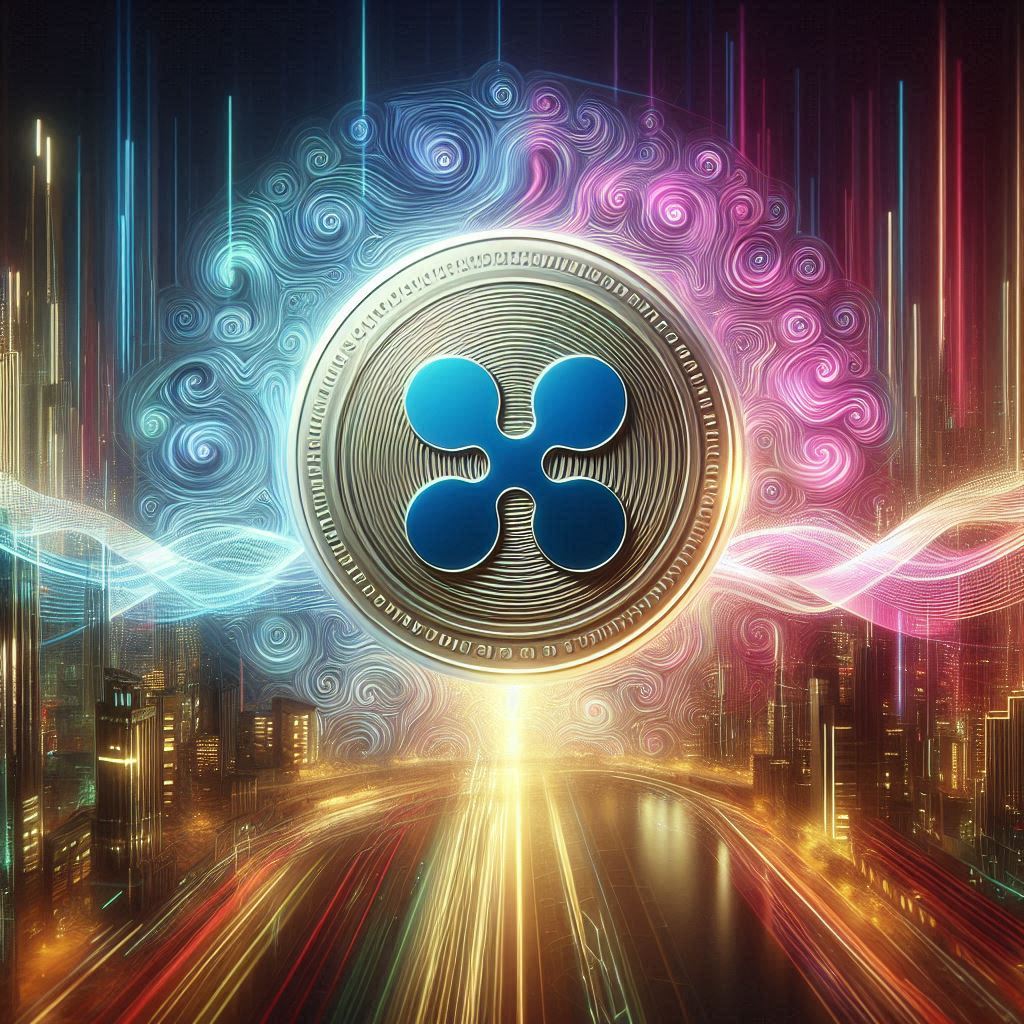
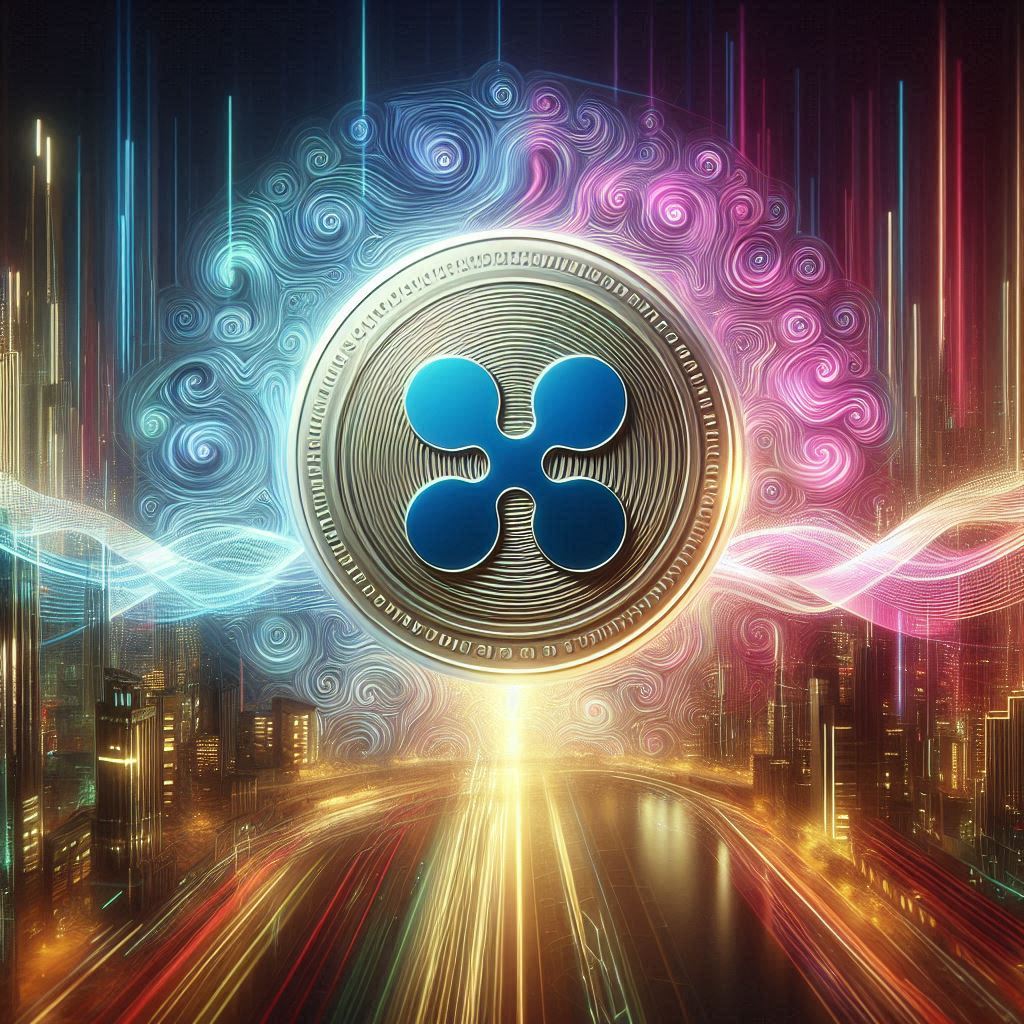
GESARA社会の新金融システムを担っているブロックチェーン企業リップル(Ripple Labs)が
米国のリスク管理および企業財務ソフトウェア企業 GTreasury を 10億ドルで買収する
ことを発表しました。
この取引は、リップル社が企業向けの決済・資金管理領域へ本格参入するための戦略的ステップであり、同社にとって2025年に入って 3件目の大型買収 となります。
買収の目的:企業財務にブロックチェーンの即時性を導入
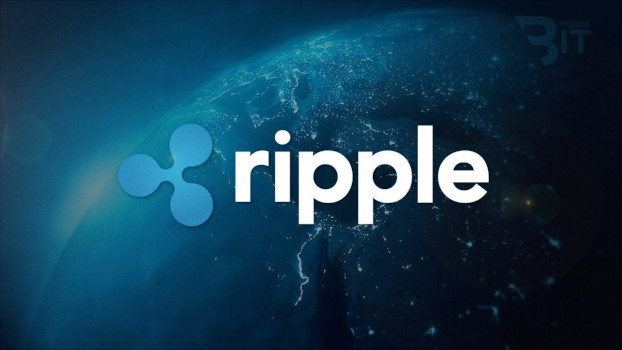
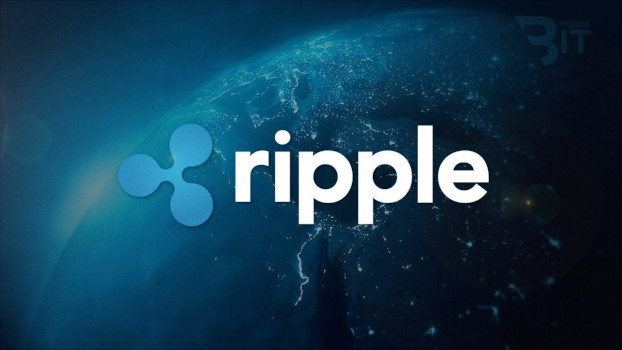
リップル社のCEO、ブラッド・ガーリングハウス氏は次のように述べています。
「資金は依然として旧来のインフラに縛られ、遅延とコストの増大を招いている。これはブロックチェーン技術が解決すべき典型的な問題です。」
この発言が示す通り、今回の買収の最大の目的は
企業が抱える「資金滞留」と「非効率な決済フロー」を根本から改善すること
にあると考えられます。
具体的にリップルは、GTreasuryの40年以上にわたる企業財務ノウハウと、リップルネットおよびXRP Ledgerのリアルタイム決済能力を融合させることで、以下を実現しようとしています。
即時送金と流動性最適化
運転資本の効率化
国際決済のリアルタイム化
リップルの戦略
今年(2025年)になってリップルの戦略的な企業買収が続いています。Qプランに沿った新金融システム(決済・送金)の構築と拡大を目標に「金融インフラ企業」としての進化を加速させています。
2025年4月: プライム証券会社「Hidden Road」を約12.5億ドルで買収
→ グローバルレポ市場へのアクセス強化、短期資産の流動化を支援
2025年8月: ステーブルコイン決済企業「Rail」を買収
→ ブロックチェーン決済を法定通貨ベースで実用化
2025年10月: 今回のGTreasury買収
→ コーポレート財務領域(TMS:Treasury Management System)にブロックチェーンを統合
この一連の動きは、リップルが単なる「仮想通貨企業」から脱却し、トークン化・ステーブルコイン・決済ネットワークを統合した新世代の金融インフラ企業 へと変貌していることを示しています。GESARA社会へ向けた軌跡に。
今後の展望:RLUSDとグローバル流動性網の統合へ


GTreasuryは世界中の多国籍企業が利用するリスク・流動性管理ソフトを提供しており、年間数兆ドル規模のキャッシュフローを処理しています。
XRP(リップル)はSWIFT(銀行間送金のキャッシュフロー)のみならず、 GTreasuryを通じて新たなキャッシュフローにも参入するということ。
リップルはこの既存ネットワークに XRP Ledgerを統合することでXRP(RLUSD)を活用した新金融システムを世界へと拡大。トランザクション(取引)をリアルタイム化することで、オンチェーン財務運営の基盤をも築こうとしていると考えられます。
リップル社はすでに、
日本のSBIホールディングスと提携し、ステーブルコイン「Ripple USD(RLUSD)」 の流通を開始
バーレーン・フィンテック・ベイ(BFB)と連携し、中東でのブロックチェーン実装を推進
といった国際的な展開を進めています。
今回のGTreasury買収は、このグローバル戦略の「財務管理インフラ部門」を担う動きであり、最終的には SWIFTを補完または代替する即時流動性ネットワーク へと発展する可能性があります。
BRICSによる金融改革!新たな決済インフラを推進中


ここ数か月間、表舞台では米国のトランプ政権動向(関税政策など)が世界的に注目されています。しかし、メディアにて取り上げられる機会は少なくとも並行して着実に推進しているのが
BRICSによる新たな決済インフラ(デジタル通貨を基盤としたもの)の整備&拡大
です。
一時期、話題となっていた「BRICS通貨(金裏付けのデジタル通貨)」の進展は、あまり見られていませんが
ロシアのデジタルルーブル、中国のデジタル人民元、インドのデジタルルピーを統合した決済インフラ
の実用化が進んでいます。
当該決済システムは、2026年から2027年の間に運用開始される予定となっており、西側諸国の銀行・SWIFTなどを仲介・利用することなく決済が行えるものに。
この新決済システムを利用することで各国のデジタル通貨間の直接交換が可能となる見込みです。
BRICS決済システム(決済プラットフォーム)による効果
BRICSが推進している新決済システム「Payプラットフォーム」は、SPFS(ロシア)、CIPS(中国)、UPI(インド)、PIX(ブラジル)などの他のBRICS諸国内決済システムを結び付ける「メッセージング&決済レイヤー」として機能します。
このPayプラットフォームを利用することで下記のような効果(目的)があると考えられます。
●ドルバイパス: 現地デジタル通貨での決済を可能にすることで、取引は BRICS決済システム内にとどまり、ドルベースの制裁や監視にさらされる可能性が軽減されます。
●ソフトな脱ドル化:現在、進行しているのは一夜にして「米ドル」を排除するものとはなっていません。あくまでも段階的な形で「現地通貨取引」「決済インフラの統合」などが進められている状況です。
二つの決済システムで世界を網羅する可能性!?


現時点までの動きを見る限り、GESARA社会の金融システム(決済インフラ)として、下記2つの決済インフラが候補となっていると考えられます。
1.XRP(XRPL)を基盤とした決済インフラ
2.BRICS「Payプラットフォーム」
前者「1」は欧米諸国・日本・中東諸国・オーストラリアなどを中心に勢力を拡大中。後者「2」はBRICS諸国を中心に推進されています。
現状は立場の異なる2つの勢力(西側諸国とBRICS諸国)にて、それぞれ新たな金融システム(決済インフラ)の構築・整備が進められている状況。それによって、上手く全世界を網羅していく計画となっていることがわかります。
最終的には、全世界がひとつに統合された決済インフラを活用することになる可能性もありますが、現時点では「2つの決済インフラによって、全世界を結び付けていく」方向性で計画が進められています。
シリアが新紙幣シリーズ発行へ!肖像や建造物を排除した“無象徴デザイン”による通貨改革


GCR(世界通貨改革)・金融システム改革において、世界各国で具現化している象徴的な出来事が「自国通貨デザインの見直し」です。
先日、シリア中央銀行が国家の象徴や人物の肖像、歴史的建造物などを完全に排除した新しい紙幣シリーズを発行する計画を発表しました。これは同国史上初の試みであり、通貨デザインにおける大きな転換点とされています。
「無象徴通貨」への大胆なシフト


新しい紙幣は、6種類の額面にて導入予定。小額から大額まで日常取引を幅広くカバーする構成となっています。中央銀行のアブドゥル・カデル・アル・フスリヤ総裁は
「すべての額面のデザイン、サイズ、素材の最終仕様は、技術的および安全面の準備完了後に発表される」
と述べているように、現時点では「新紙幣計画」が発表された段階で具体的なデザインはこれから設計・発表される予定とのことです。
今回の出来事に関して注目すべきは、単なる美的刷新ではなく
通貨の中立性・透明性・デジタル互換性の向上
にあります。
政治的・宗教的なシンボルを取り除くことで、通貨が象徴として持つ“分裂の重み”を軽減し、国内外での信頼回復を目指すとしています。
これは新たなGESARA社会(五次元世界)に沿った要素となるもの。要注目の動きと捉えています。
通貨改革の背景:信頼回復と効率化


シリアポンド(シリアの自国通貨。現地ではリーラと呼ばれています。)は、長年の内戦・制裁・インフレにより急激な価値下落を経験してきました。その中で、通貨への信頼を再構築するための心理的・実務的な刷新が求められていました。
新デザイン紙幣(シリアポンド)の導入は、次の目的を兼ね備えています。
・劣化した旧紙幣の交換・更新
・偽造防止技術の強化
・印刷コストの削減
・デジタル通貨時代への適応
アル・ハッサリ氏は「新紙幣は流通管理を厳格化しつつ、マネーサプライを増加させるものではない」と強調。短期金融市場の監視や流動性調整などの政策手段を併用し、インフレや投機のリスクを抑えるとしています。
世界的なトレンドとGESARA社会へ向けた金融改革


この「ミニマリスト」なデザインは、政治的中立性を重視する世界的潮流とも一致します。
近年、通貨を“国家のメッセージツール”から“機能的決済媒体”へと再定義する動きが拡大
しており、これはGESARA社会に沿った要素となるもの。シリアもその流れに加わった形です。
今回の動きは「危機後の安定と再生を象徴する通貨リセット」となるもの。デジタル決済・ブロックチェーン統合を見据えた将来戦略の一環とみることも出来そうです。
今回の刷新は、単に紙幣のデザインを変えるものではなく、「政治から経済へ、象徴から機能へ」という転換を象徴しています。
シリアにとってこの新紙幣は、通貨への信頼回復と経済再建への第一歩となると共に、GESARA社会へ向けた大切な準備となると考えています。












